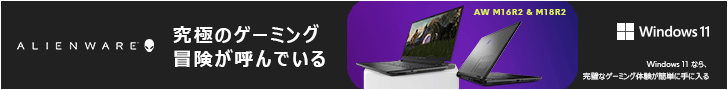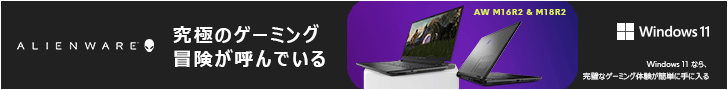|
岩国・錦帯橋を渡り土手沿いの道路を右手に20〜30m行くと吉香公園の方に下る道があり、すぐ前方に佐々木小次郎の像があるのをご存じだろうか。
「物干し竿」と言われた長剣を右に構え、片膝着いて「燕返し」で武蔵に切りかかろうとしている像のように見えるが、その像を見た時、なぜこの地に小次郎?という疑問が湧いた。
小次郎の「燕返し」は岩国で生み出された?
佐々木小次郎は宮本武蔵以上に出自等が明らかでなく、舟島(俗に言う巌流島)で武蔵と果し合いを行わなければ存在する危ぶまれ、架空の人物と言われかねない。
小次郎がその名を留めているのは講談や映画、小説の中のみで、それも武蔵との関係で登場し、彼単独で、つまり彼を主役にした小説、映画も存在しない(私が知る限りでは)わけで、それだけ彼の生涯はなぞに包まれている。
早い話、第1級の資料には登場しないのだから小次郎の人物像は出生地、出生年、経歴等も裏付けが取れない謎の人物である。
これが好都合、というのは言い過ぎだが後世の創作に関わる人間にとっては実に好都合(また言ってしまった)で、どうにでも創り上げることができる。
ならば小次郎を主役にした小説や映画がもっとあってもいいようなものだが、それがない。
それはさておき、小次郎と岩国の関係である。わざわざ小次郎の像を建立するぐらいだから小次郎は岩国に滞在したことがあるとか、岩国藩に仕えた、あるいはこの地に道場を開き藩士に巌流を教えたなどの関係が分かる資料があるのだろうと考えたが、それに類するものはなかった。
では、なぜと疑問は深まるばかりだ。錦帯橋の麓の河川敷には「巌流ゆかりの柳」まであるが、それらはただ単に観光客を惹き付けるための看板で、史実とは関係ない世界なのかと訝ってしまうが、観光客を呼び込むめだけの材料、史実とは関係ないフィクションを基に、さも史実であるかのように装っていたわけだ。
だからといって岩国市を責めるわけにはいかない。いまやどこの地もドラマにあやかり、史実を無視したPRを行っているわけで、それを見た観光客などはフィクションを信じて帰っていく。
小次郎の像を建てさせたのは吉川英治である。といっても彼が小次郎像建立を働きかけたわけではない。恐らく映画かTVで「宮本武蔵」がブームになった時、その人気にあやかろうと岩国市が小次郎像を建てたのだろうが、武蔵でなくなぜ小次郎像かといえば、小説「宮本武蔵」の中に小次郎がこの地で「燕返し」を生み出したことにされていたからである。
錦帯橋の麓の柳の枝が燕を打つのを見て「燕返し」の術を得た。
吉川英治が「宮本武蔵」の中でそう記し、創作した。
もちろん、裏付ける文献や資料はない。武蔵が子供の頃、両手にバチを持ち太鼓を打つ姿を見て二刀流を編み出したという創作同様、根拠がない、かなりいい加減な(あり得ない)話だが、それを読者に信じ込ませるほど、当時(それ以後も)「宮本武蔵」は国民の圧倒的支持を得、読まれた。
因みに武蔵を慕う「お通」は完全に吉川英治の創作で、現実にはそのような女性の陰などまったく存在しないのだが、いまだに「お通」の存在を信じている人が結構いるのは吉川英治の力である。
(2)に続く
|