|
同じ造るなら他社にないものを造りたい。
「酸味で差別化をしたかったのです」
従来、焼酎を造るのに使われていた黒麹で日本酒を造った理由を、池亀酒造の6代目、蒲池輝行はこう語る。
減圧蒸留が主流の時代に敢えて常圧蒸留による本格焼酎造りにこだわり、開発したのが「ちくご胡座(あぐら)」。その評判がよかったので、いよいよ日本酒造りに着手したのだった。
「うちは元々日本酒メーカーなので、やはり日本酒を造りたかった。それも本格的な日本酒を」
それまでも日本酒を造っていなかったわけではない。吟醸酒なども造りはしていたが、輝行の目には「問屋任せにして、力の入れ方が違う」と映っていた。
中小の蔵元は自社で営業できるほどの力も余力もなく、いきおい販売は問屋に頼らざるをえないのが実状だ。そのため問屋の言われるままにレギュラー酒を造ってきたが、価格面では大手に対抗できず、そこに日本酒離れが重なり、いずこも売り上げは下降線を辿っていた。
その一方で、こうした状況を打破すべく高級路線、個性化路線へ舵を切り、吟醸酒や山廃、生酛づくりといった、こだわりの高級酒に活路を求める蔵元も現れ出していた。
なかでもフルーティーな香りで、サラッとして飲みやすい吟醸酒は、いままで日本酒とは程遠い存在だった女性層や新しいファンを取り込み、いまや一定のシェアを確保しているし、古くからの日本酒通を主ターゲットにした山廃、生酛づくりといったこだわりの酒造りをする蔵元も出ている。
こうした動きに比べ、池亀酒造の取り組みは明らかに遅れていた。
「このまま問屋任せで、いわれるままにレギュラー酒を造っていたのでは蔵の将来は見えている。かといって、他社の後追いをして山廃、生酛を造るのも面白くない。同じ造るなら他社にないものを造りたい」
輝行はそう考えていた。
キーワードは酸味--。
これはすんなり決まった。山廃、生酛が酸味のある日本酒だということもあったが、酸味がある方が飲み飽きないし、料理との相性もいいからだった。
問題はどのような酸味にするかである。
分かりやすくいうと山廃、生酛は乳酸系の酸味であり、少し温めると旨みが出てくる。そのため、飲み方もぬる燗ぐらいがおいしい。
すでに山廃、生酛で支持されている乳酸系の酸味を使いつつ、他の部分で個性化を図る方法もあったが、輝行はそうしなかった。あくまでもオリジナルにこだわった。大学院での研究生活と、その後メルシャン等で新製品開発に携わってきた技術者の誇りがそうさせたのかどうか分からないが、他社にない酸味で勝負したかった。
(次に続く)
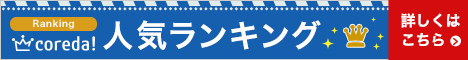

|

